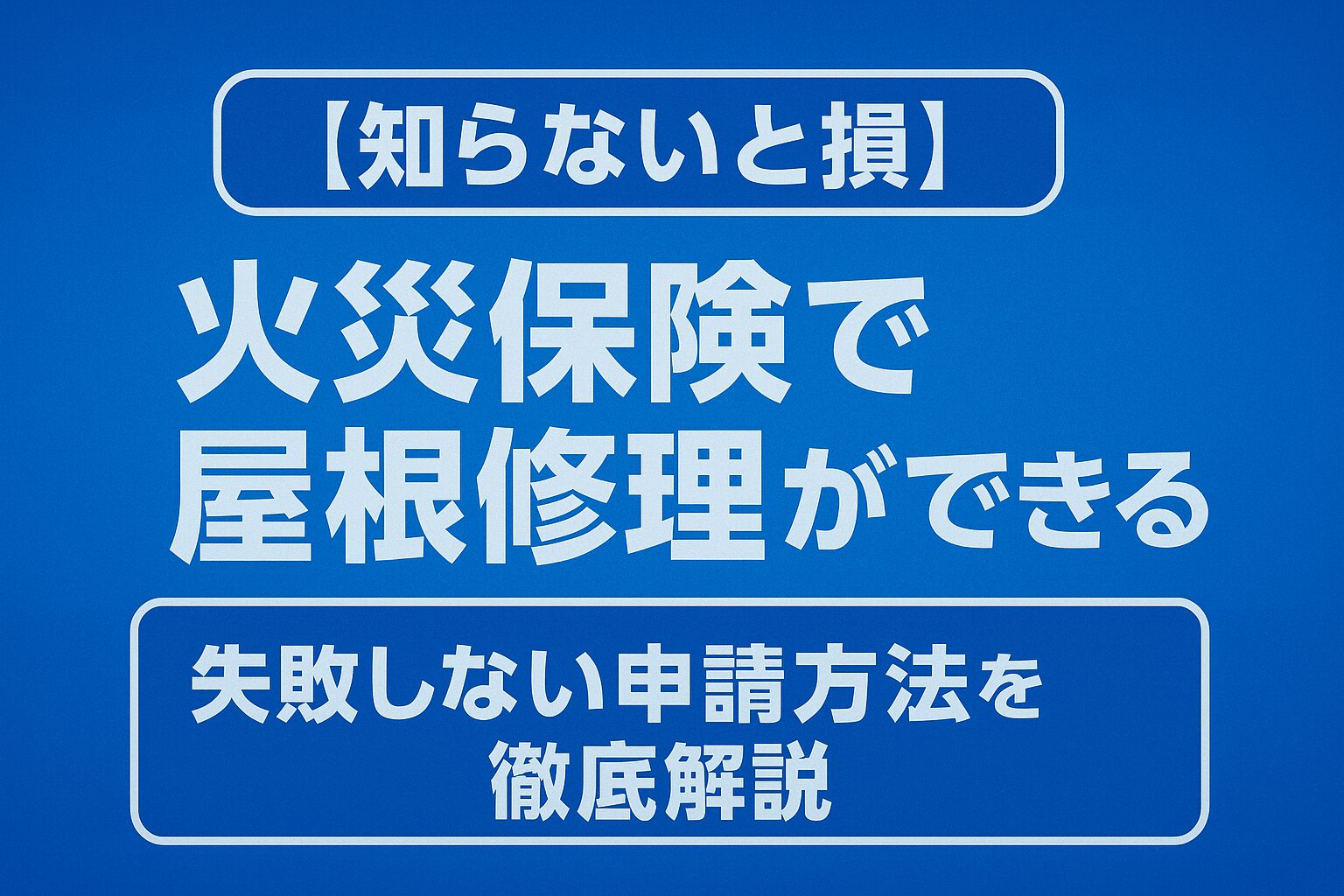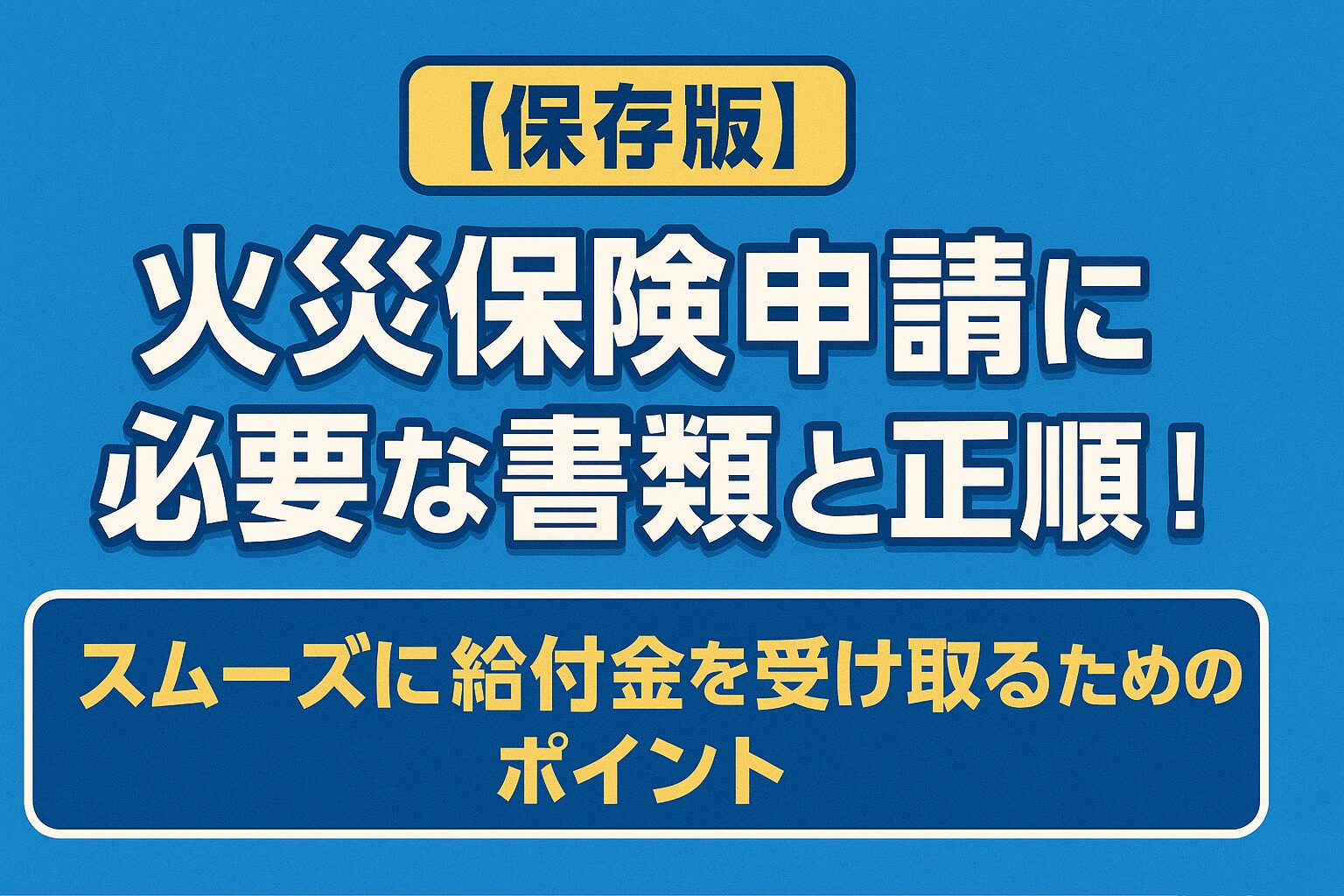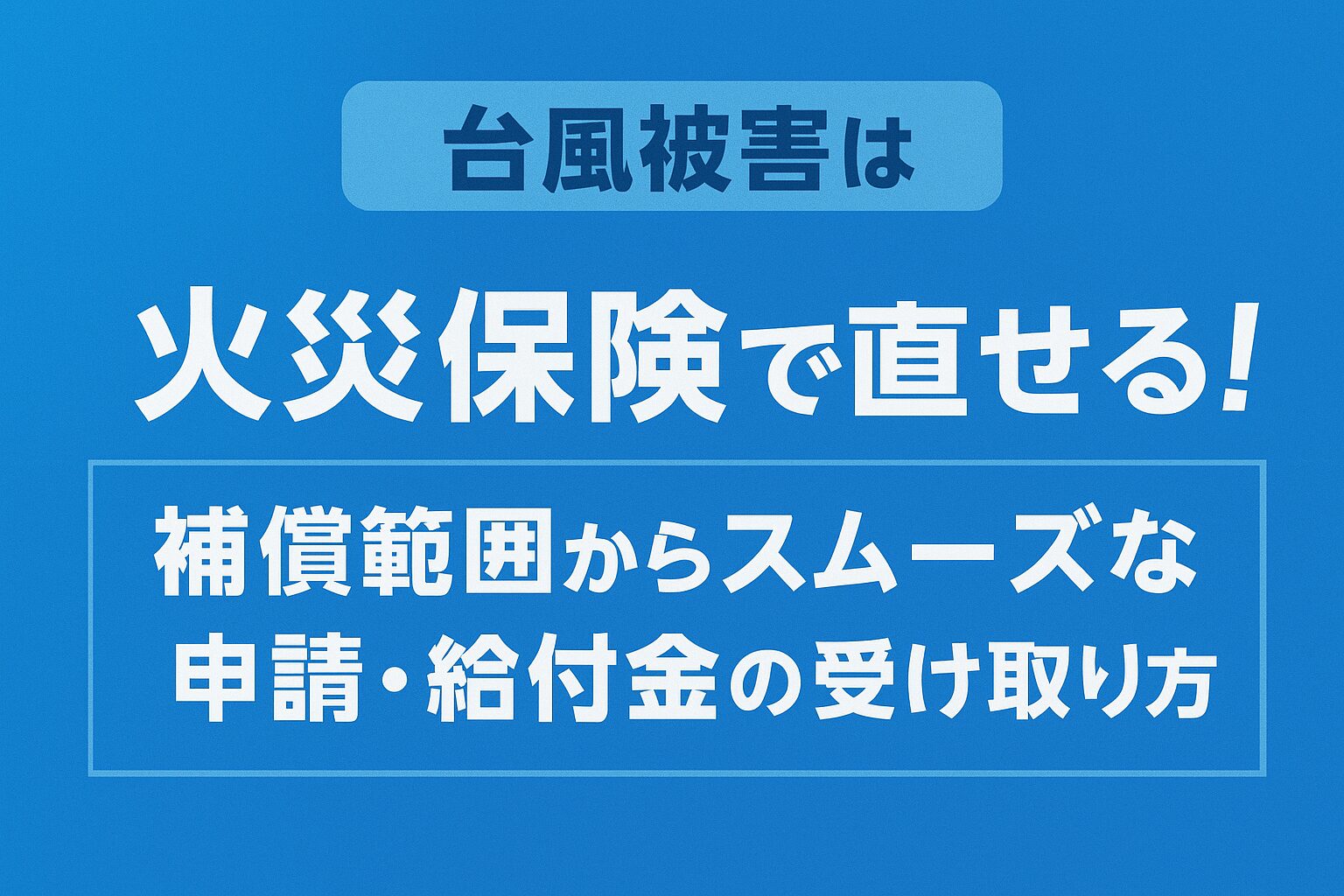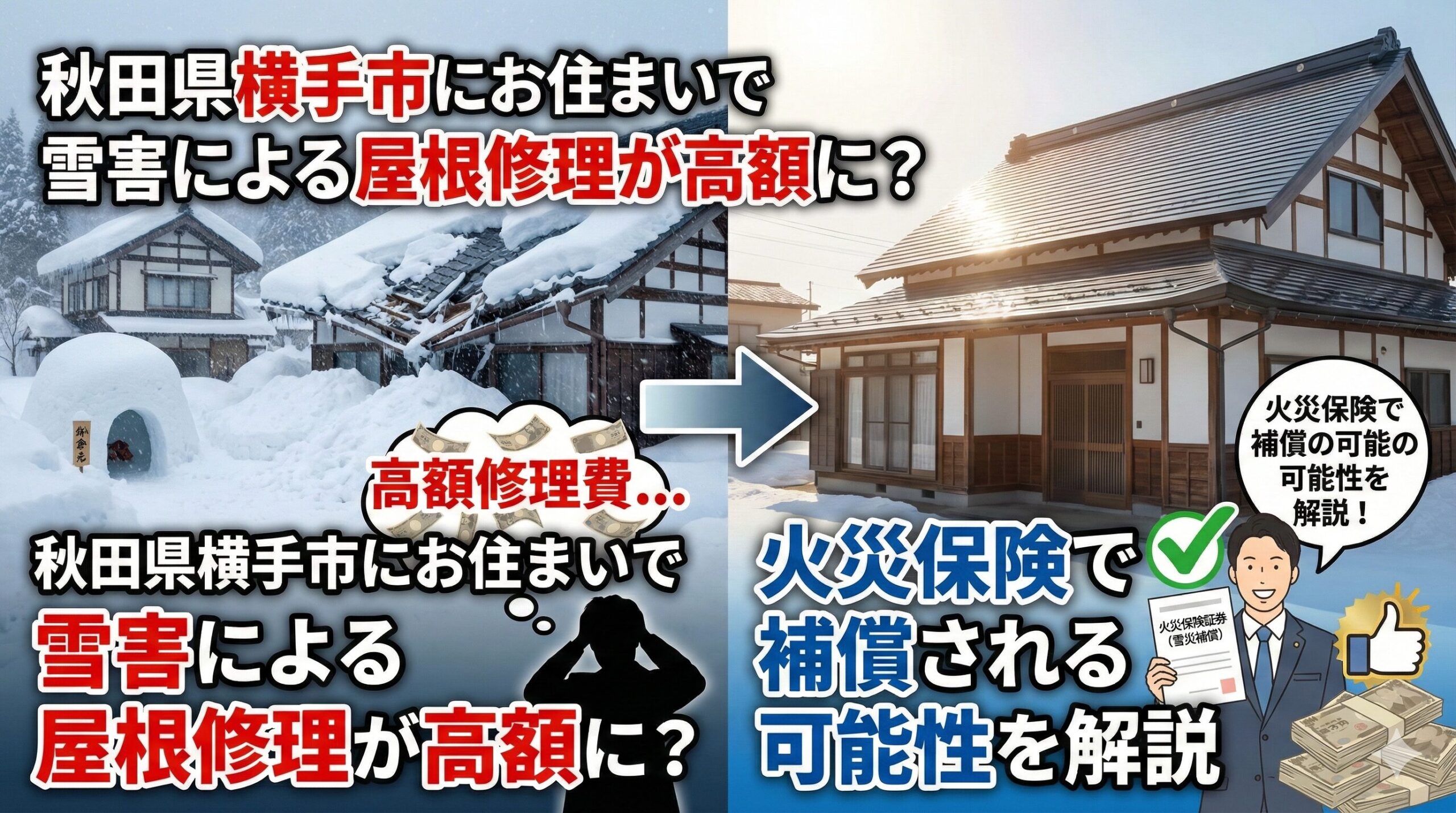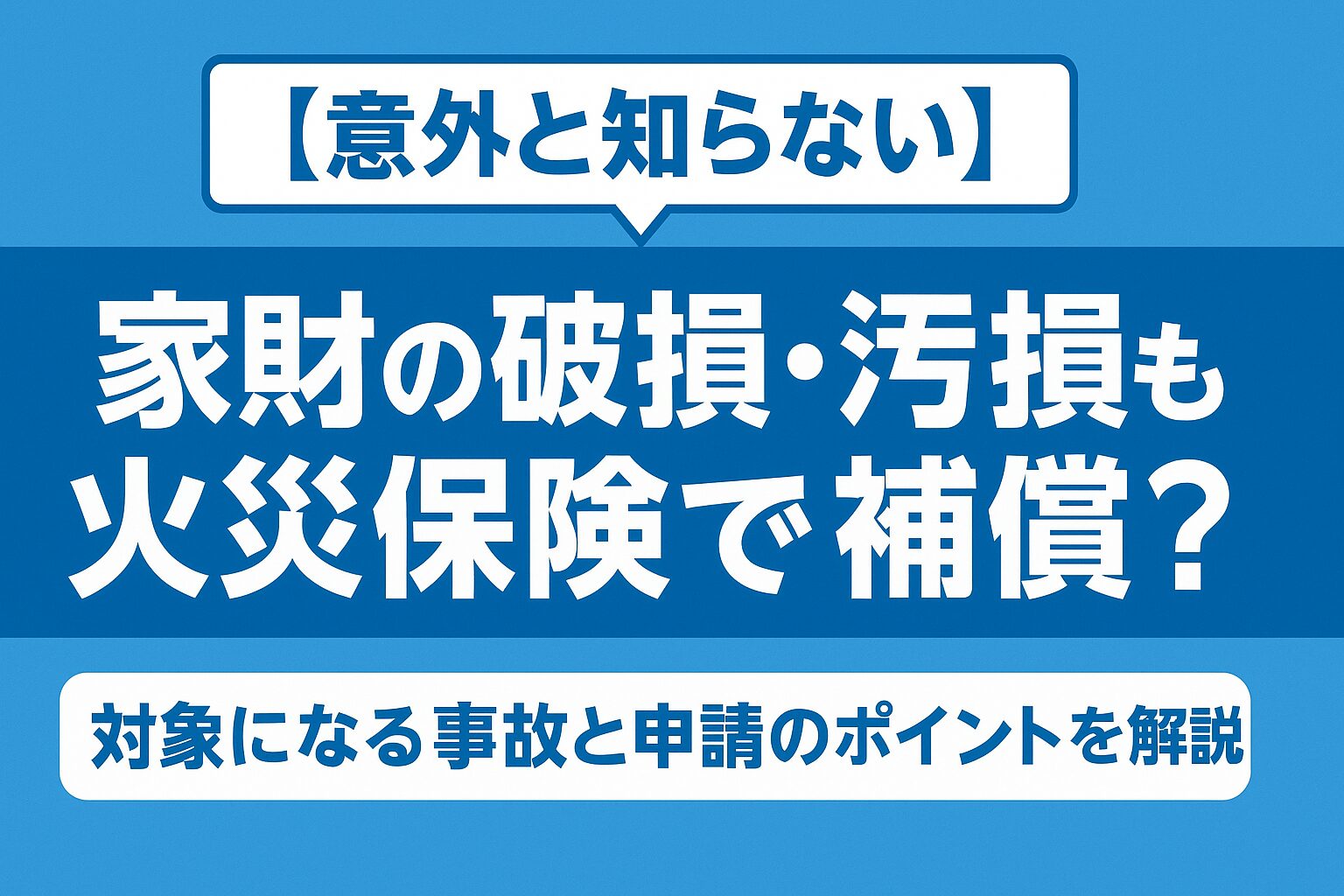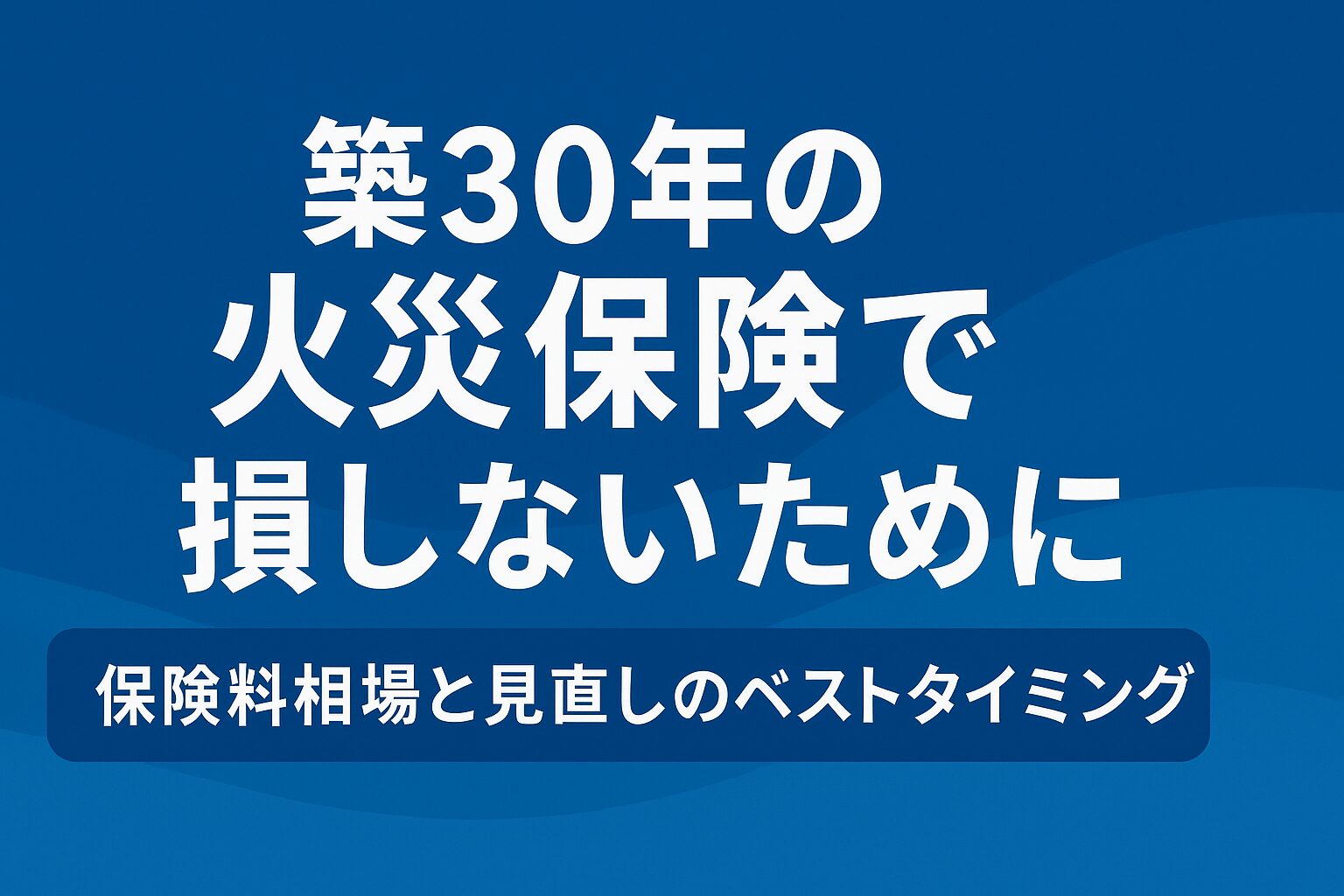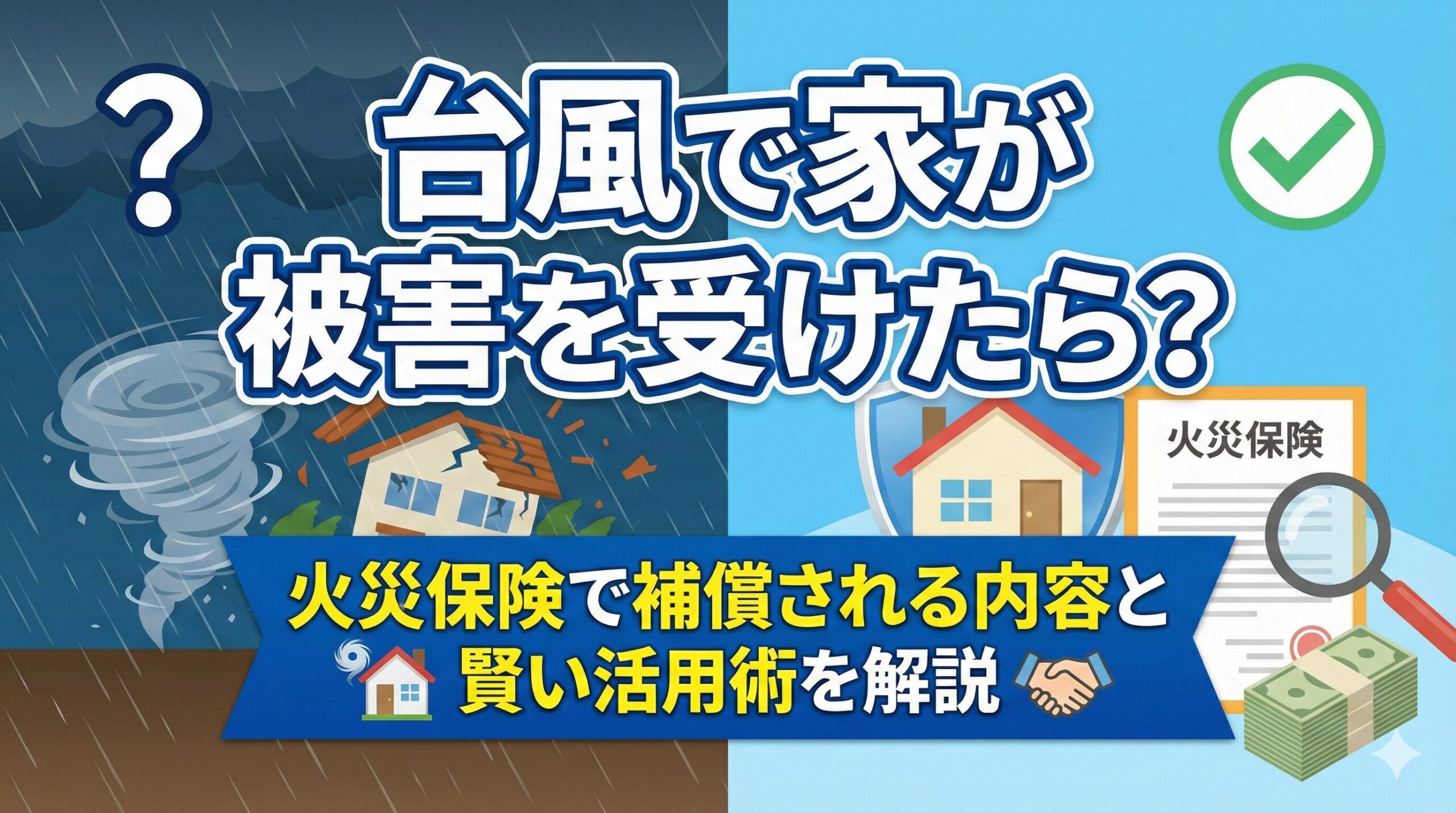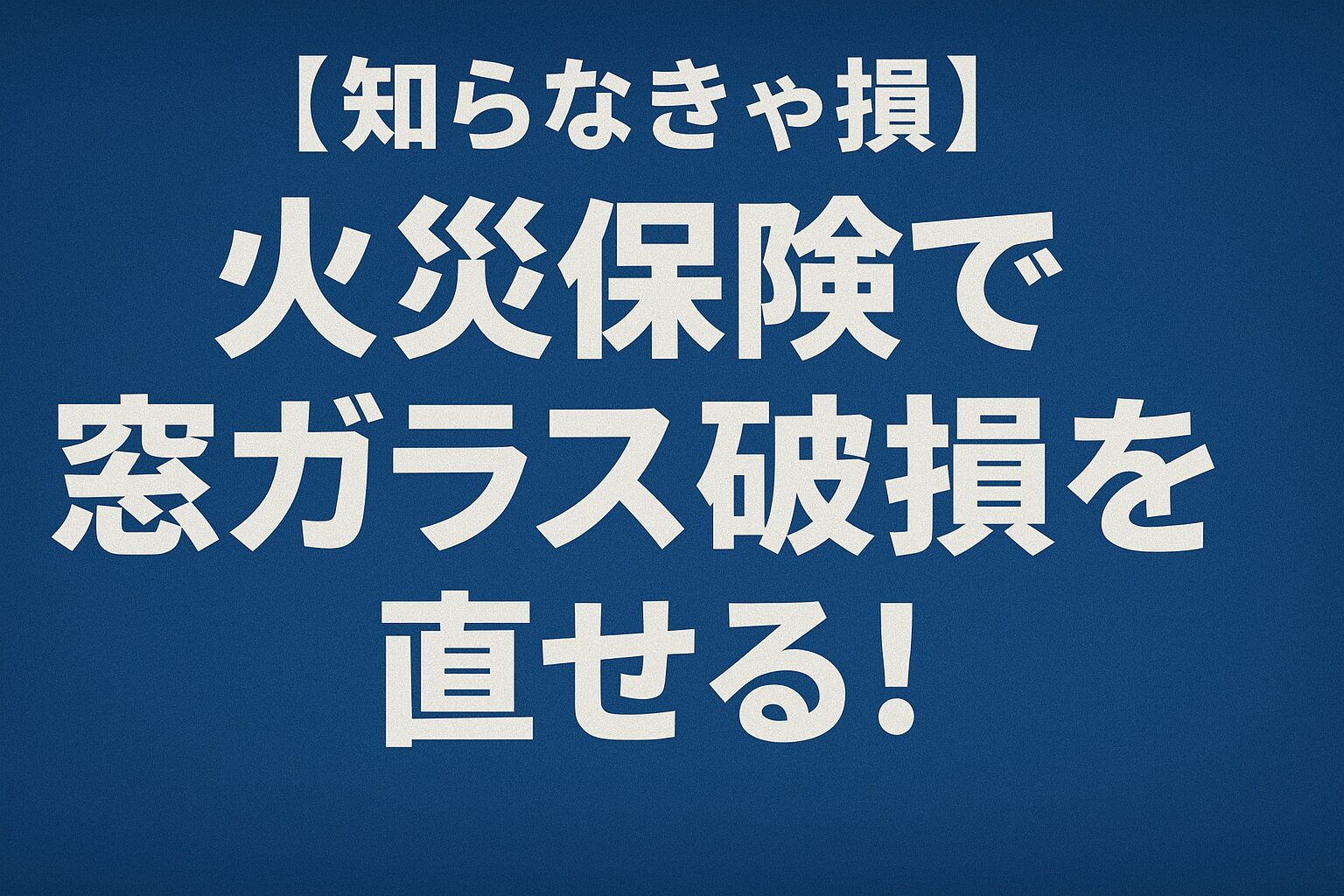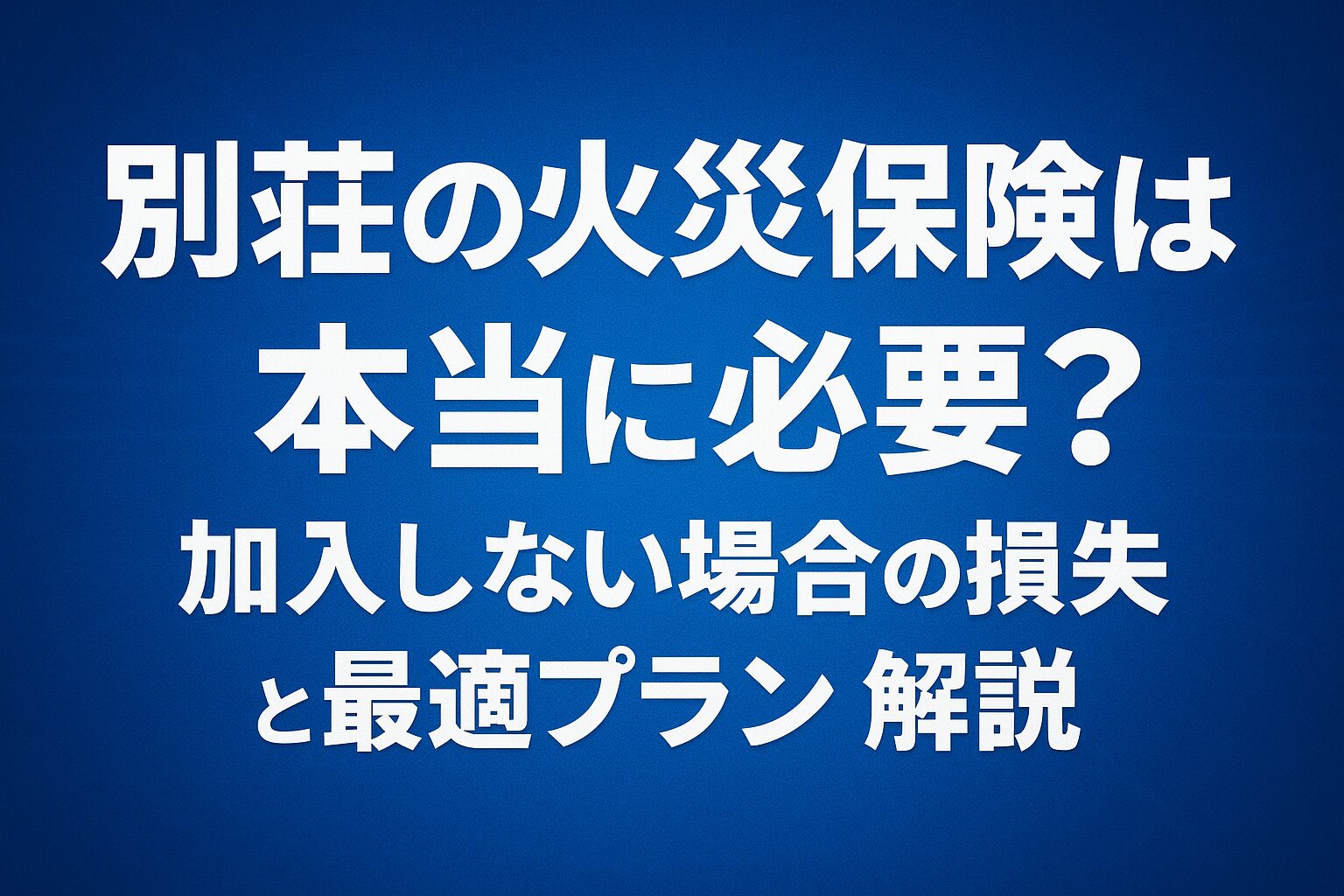2025年10月8日
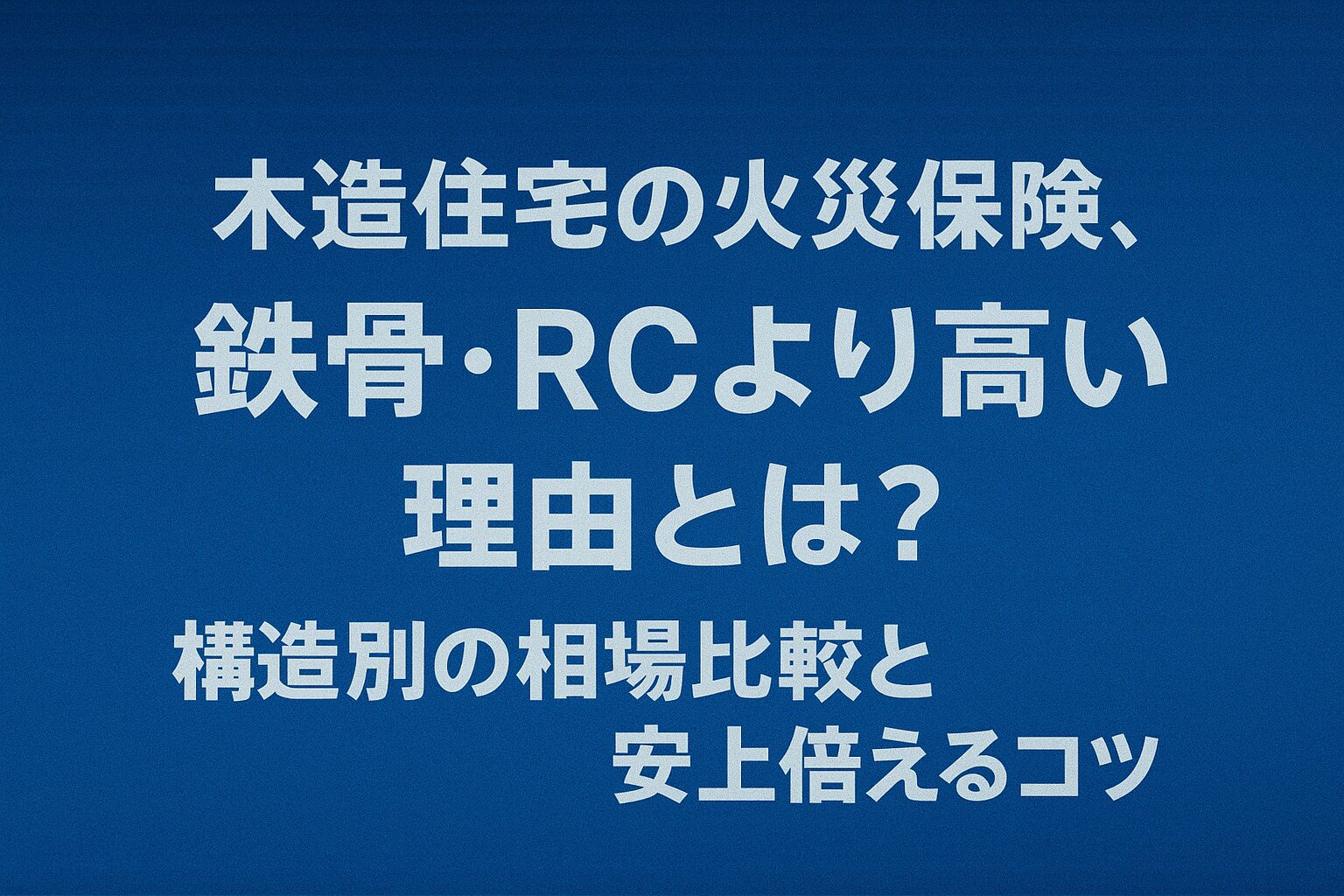
目次
保険料を決めるたった一つのルール。建物の「燃えにくさ」を表す構造級別とは
木の香りに包まれ、夏は涼しく、冬は暖かい。日本の気候風土に寄り添うように建てられた木造住宅は、私たちの暮らしに、何物にも代えがたい安らぎと、ぬくもりを与えてくれます。
しかし、夢のマイホームでの新生活を前に、あるいは、長年住み慣れた我が家の火災保険を見直そうとしたとき、一枚の見積書を見て、その金額に思わず目を見開いてしまった、という経験はございませんか。
「えっ、木造の家って、火災保険がこんなに高いの?」
「マンションに住む友人の保険料と、倍以上も違うのはどうして…?」
その驚きと疑問の裏には、火災保険の保険料が決まる、極めてシンプルで、しかし、あまり知られていない「仕組み」が存在します。
その理由は、単に「木は燃えやすいから」という、漠然としたイメージだけではありません。
この章では、あなたの家の火災保険料を決定づける、たった一つの重要なルール「構造級別」という名の設計図を、一つひとつ丁寧に読み解いていきます。
この仕組みを理解することこそが、保険料が高い理由に心から納得し、そして、その保険料を賢く安くするための、全ての始まりとなるのです。
火災保険料は「リスクの大きさ」で決まる
まず、すべての保険に共通する、大原則からお話しさせてください。
保険とは、たくさんの人が少しずつお金(保険料)を出し合って、大きな共有の財布を作り、その中から、実際に困ったこと(事故)が起きた人にお金を支払う、という「助け合い」の仕組みで成り立っています。
この仕組みを公平に保つためには、ルールが必要です。
それは、「事故にあう可能性(リスク)が高い人には、少し多めに保険料を負担してもらい、リスクが低い人には、その分、保険料を安くする」というものです。
火災保険も、全く同じ考え方で作られています。
つまり、火災が発生するリスクが高い(燃えやすく、被害が大きくなりやすい)と判断される建物ほど、保険料は高く設定され、逆に、火災リスクが低い(燃えにくく、被害が広がりにくい)建物ほど、保険料は安くなるのです。
そして、あなたの家が、この「リスクが高いのか、低いのか」を客観的に判断するための、共通のモノサシ。それこそが、これからご説明する「構造級別」なのです。
あなたの家はどれ?3つの構造クラス「M構造・T構造・H構造」
保険会社は、建物を、その柱の素材や、壁、床などの構造から、主に3つのクラスに分類し、それぞれのリスクレベルを評価しています。
少し専門的な響きに聞こえるかもしれませんが、ご自身の家を思い浮かべながら、読み進めてみてください。
・M構造(マンション構造)
これは、3つのクラスの中で、最も火災リスクが低く、保険料が一番安くなるクラスです。
その名の通り、鉄筋コンクリート(RC)造のマンションなどが、このM構造に分類されます。
コンクリートは、それ自体が燃えない素材(不燃材料)であり、壁や床も厚いコンクリートで作られているため、万が一、一つの部屋で火災が発生しても、他の部屋へ燃え広がる可能性が極めて低い、と評価されます。
・T構造(耐火構造)
これは、M構造の次に火災リスクが低く、保険料が中間レベルに設定されているクラスです。
代表的なのは、柱が鉄骨で組まれた、鉄骨造の戸建て住宅です。
また、コンクリートブロック造や、耐火建築物と認められた建物も、このT構造に分類されます。
そして、ここが非常に重要なのですが、ある特定の基準を満たした「木造住宅」も、このT構造とみなされることがあります。これについては、後ほどたっぷりと、そして詳しく解説します。
・H構造(非耐火構造)
これが、3つのクラスの中で、最も火災リスクが高いと判断され、保険料が一番高くなるクラスです。
そして、私たちが一般的にイメージする、ごく普通の「木造住宅」が、このH構造に分類されます。
なぜ、木造住宅がこのH構造に分類されてしまうのか。その具体的な理由を、次に見ていきましょう。
なぜ木造住宅は「H構造」に分類され、保険料が高くなるのか?
「やっぱり、木造は一番リスクが高いんだ…」
そう思われたかもしれません。では、保険会社は、具体的に木造住宅のどのような点を「リスクが高い」と評価しているのでしょうか。
その理由は、主に3つの側面から説明することができます。
理由1:火災発生時の「燃焼リスク」
これは、最もイメージしやすい理由でしょう。建物の主要な構造部材である柱や梁、壁などが、木という可燃性の素材で作られているため、一度火がつくと、それ自体が燃料となって燃え広がってしまいます。
理由2:火が広がりやすい「延焼リスク」
木造住宅は、構造上、壁の中や天井裏などに空間が多く、そこを空気の通り道として、火が急速に建物全体へ回りやすい、という特性があります。
鉄筋コンクリート造の建物に比べて、部分的な火災(部分焼)で収まらず、建物全体が焼失してしまう「全焼」に至るまでの時間が、短い傾向にあるとされています。
理由3:消火活動による「水濡れ損害のリスク」
万が一、火災が発生した場合、消防による消火活動では、大量の水が使われます。
木材は、水を吸収すると、膨張したり、強度が低下したり、カビが発生したりする原因となります。
たとえ火で燃えなかった部分であっても、消火活動で使われた水によって、壁や床、天井などが深刻なダメージを受け、結果として、建物全体の損害額が大きくなりやすい、という側面も考慮されているのです。
これらの複合的なリスク評価から、一般的な木造住宅は「H構造」に分類され、他の構造の建物に比べて、保険料が高めに設定されている。これが、あなたの疑問に対する、最も正確で、そして論理的な答えとなります。
構造級別かんたん早見表
あなたの家は、どのクラスに当てはまりますか?
| 構造クラス | 主な建物の種類 | 保険料レベル |
|---|---|---|
| M構造 (マンション構造) |
・鉄筋コンクリート(RC)造の共同住宅 ・耐火建築物の共同住宅 |
安い |
| T構造 (耐火構造) |
・鉄骨造の戸建て ・コンクリートブロック造の戸建て ・省令準耐火構造の木造戸建て |
中間 |
| H構造 (非耐火構造) |
・一般的な木造戸建て | 高い |
こんなに違う!木造・鉄骨・RC造、年間保険料のリアルな目安
火災保険の保険料が、「構造級別」というモノサシで決まる、という仕組みは、ご理解いただけたかと思います。
「理屈は分かったけれど、じゃあ、実際にどれくらいの金額の差がつくものなの?」
多くの方が、次に知りたいのは、そのリアルな数字ではないでしょうか。
この章では、具体的なシミュレーションを通じて、木造(H構造)、鉄骨造(T構造)、そしてRC造(M構造)の火災保険料が、実際にどれほど違うのかを、肌感覚で掴んでいただきたいと思います。
ここで提示する数字は、あなたの家の保険料が高いのか、あるいは妥当なのかを判断する上での、一つの大きな目安となるはずです。
比較の前に。保険料を左右する共通の前提条件
具体的な金額の比較に入る前に、一つだけ、とても大切なことをお話しなければなりません。
火災保険料は、建物の構造だけでなく、所在地や補償内容、保険金額など、さまざまな要素によって変動します。
ですから、ただ単純に「木造は〇円、鉄骨は〇円」と比較しても、その前提条件がバラバラでは、意味のある比較にはなりません。
そこで、今回は、以下の通り、すべての条件を統一した上で、建物の構造級別だけを変えた場合に、保険料がどのように変化するのかを、シミュレーションしてみます。
シミュレーションの前提条件
- 所在地:東京都
- 建物:戸建て住宅(マンションはM構造の参考)
- 建物保険金額:2,000万円(新価)
- 家財保険金額:500万円
- 補償内容:基本的な火災、風災、水濡れなどに加え、水災補償も付帯した標準的なプラン
- 保険期間:10年間の長期契約を一括で支払い、その金額を1年あたりに換算した「年額換算保険料」
- 割引等:各種割引は適用しない状態での比較
これらの条件をベースに、いよいよ、構造ごとの保険料の目安を見ていきましょう。
【シミュレーション】年間保険料は最大3倍以上の差に!
上記の共通条件で、保険会社数社の見積もりを平均化すると、年間の保険料の目安は、おおよそ以下のようになります。
【M構造】(鉄筋コンクリート造のマンションなどを想定)
→ 年間保険料の目安:約 8,000円 ~ 12,000円
【T構造】(鉄骨造の戸建てなどを想定)
→ 年間保険料の目安:約 15,000円 ~ 25,000円
【H構造】(一般的な木造の戸建てを想定)
→ 年間保険料の目安:約 30,000円 ~ 50,000円
いかがでしょうか。その差は、一目瞭然です。
最も安いM構造と、最も高いH構造とを比べると、その差は、実に3倍から4倍以上にも開いていることが分かります。
同じ2,000万円の価値を持つ建物であっても、その構造が違うというだけで、年間に支払う保険料に、数万円単位の大きな差が生まれてしまうのです。
もちろん、これはあくまで、ある一定の条件下での目安の金額です。
あなたの家の所在地や、補償内容、保険金額によって、この数字は上下しますが、この「構造による保険料の比率」は、どの保険会社でも、おおむね似たような傾向になります。
あなたが木造住宅の見積もりを見て、「高い!」と感じたその感覚は、決して間違いではなかった、ということが、この数字からお分かりいただけるかと思います。
なぜここまで差がつくのか?保険料率のカラクリ
「それにしても、なぜ、ここまで極端な差がつくのだろう?」
そう不思議に思われるかもしれません。その秘密は、保険料を計算するための「計算式」の中に隠されています。
火災保険の保険料は、非常にシンプルに表現すると、以下の計算式で算出されます。
保険料 = 保険金額 × 保険料率
「保険金額」とは、あなたが設定した、建物や家財の補償額(今回の例では、建物2,000万円)のことです。
そして、この式の中で、建物の構造によって大きく変動するのが、「保険料率(ほけんりょうりつ)」と呼ばれる、掛け率なのです。
この保険料率は、過去に発生した膨大な火災事故のデータを分析し、「この構造の建物は、これくらいの確率で、これくらいの損害が出る」という、統計的なリスクに基づいて、構造級別ごとに細かく設定されています。
そして、先ほどのシミュレーションで示した通り、H構造のリスクは、M構造のリスクの3倍以上と評価されているため、この「保険料率」そのものが、H構造はM構造の3倍以上に設定されている、というわけです。
同じ保険金額2,000万円に、3倍以上も違う掛け率を乗じるのですから、最終的に算出される保険料に、大きな差がつくのは、当然の結果といえるのです。
あなたの木造住宅、実は安くなるかも?「省令準耐火構造」という魔法の言葉
「木造住宅はリスクが高いから、保険料が高いのは仕方がないんだな…」
ここまで読み進めて、そう納得し、少しがっかりした気持ちになっている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、どうか、ここで諦めるのは、まだ早すぎます。
実は、あなたの木造住宅にかけられた「H構造(非耐火構造)」というレッテルを覆し、保険料を劇的に、それこそ鉄骨造の家と同じレベルまで引き下げることができる、強力な「切り札」が存在するのです。
それが、「省令準耐火構造(しょうれいじゅんたいかこうぞう)」という、少し長くて難しそうな名前の構造です。
この章では、高い保険料に悩む、すべての木造住宅オーナーにとっての救世主ともいえる、この「省令準耐火構造」の秘密と、その驚くべきメリットについて、これ以上ないほど分かりやすく、そして詳しく解説していきます。
木造なのに鉄骨並み?「省令準耐火構造」とは何か
「省令準耐火構造」とは、一体どのようなものなのでしょうか。
ごく簡単に言うと、それは、普通の木造住宅に、さまざまな「火に強い工夫」をプラスすることで、建築基準法が定める「準耐火構造」と同等の、高い防火性能を持つと認められた、特別な木造住宅のことです。
その「火に強い工夫」は、主に3つのポイントに集約されます。
1.【隣家からの延焼防止】
もし、お隣の家で火事が起きても、簡単には燃え移ってこないように、屋根や外壁に、燃えにくい素材(不燃材料)を使用するなどの工夫がされています。
2.【各室防火】
万が一、家の中の一つの部屋から出火しても、壁や天井の内部に、火に強い「石膏ボード」を二重に貼るなどして、部屋全体がすぐに火の海になるのを防ぎます。
3.【他室への延焼遅延】
火が、壁の中や天井裏を伝って、他の部屋へ燃え広がるのを、できるだけ遅らせるための工夫(ファイヤーストップ材など)が、各所に施されています。
これらの工夫によって、省令準耐火構造の住宅は、火災が発生しても、全焼に至るまでの時間を長く稼ぐことができ、その間に家族が安全に避難したり、消防の初期消火が間に合ったりする可能性が、格段に高まるのです。
そして、この高い防火性能が、火災保険の世界で、絶大な効果を発揮します。
この省令準耐火構造の基準を満たしていると認められた木造住宅は、保険料を計算する際の構造級別が、最も高い「H構造」から、一つ下の「T構造」へとランクアップするのです。
つまり、あなたの家が、材質は「木」でありながら、保険料の世界では「鉄骨」と同じように扱ってもらえる、という、まさに魔法のような現象が起こるのです。
保険料はどれくらい安くなる?衝撃のビフォー・アフター
では、構造級別が「H構造」から「T構造」に変わることで、保険料は実際に、どれくらい安くなるのでしょうか。
先ほどのシミュレーションの数字を、もう一度見てみましょう。
【ビフォー】H構造(一般的な木造住宅の場合)
→ 年間保険料の目安:約 30,000円 ~ 50,000円
【アフター】T構造(あなたの家が、もし省令準耐火構造だった場合)
→ 年間保険料の目安:約 15,000円 ~ 25,000円
その差は、一目瞭然です。保険料は、ほぼ半額になるのです。
年間の差額は、安くても1万5,000円、多ければ2万5,000円にもなります。
もし、火災保険を10年間の長期契約で結んだとすれば、その差額は、10年間で15万円から25万円にも達します。
この事実を知っているか、知らないか。そして、ご自身の家が、この「省令準耐火構造」に該当するかどうかを確認するか、しないか。
その、ほんの少しの知識と行動の違いが、あなたの家計に、これほど大きなインパクトを与える可能性があるのです。
我が家は省令準耐火?確認するための3つの方法
「うちの家も、もしかしたら、そうなのかもしれない!」
そう思われたあなたのために、ご自身の家が省令準耐火構造に該当するかどうかを、ご自身で確認するための、具体的な方法を3つご紹介します。
方法1:家の「建築確認申請書」を見てみる
これは、最も確実な方法です。家を建てた際に、必ず作成されている「建築確認申請書(の副本)」という書類一式が、お手元に保管されているはずです。
その中の、「第四面」と呼ばれる書類の仕様の概要欄などに、「省令準耐火構造」や、それに類する記載がないかを確認してみましょう。
方法2:家を建てたハウスメーカーや工務店に問い合わせる
書類を探すのが大変、という方は、実際にその家を建築した会社に直接問い合わせてみるのが、手っ取り早い方法です。
「火災保険の契約で必要なので、我が家が省令準耐火構造に該当するかどうか、教えてほしい」と伝えれば、当時の設計図や仕様書などから、すぐに調べてもらえるはずです。
方法3:「適合証明書」を確認する(フラット35利用者)
もし、あなたが住宅ローン「フラット35」を利用して、その家を建てたのであれば、省令準耐火構造である可能性は非常に高いです。
なぜなら、フラット35の融資では、省令準耐火構造の住宅は、金利の優遇措置を受けられるため、多くのハウスメーカーが、標準仕様として採用しているからです。
その場合、住宅金融支援機構が発行する「適合証明書」に、その旨が記載されています。
保険会社にどう伝えればいい?必要な証明書類
ご自身の家が、省令準耐火構造であることが判明したら、あとはその事実を、保険会社にきちんと証明するだけです。
保険の見積もりを依頼する際や、契約手続きの際に、以下のいずれかの書類を提示することで、あなたの家は、晴れて「T構造」として、適正な安い保険料で契約することができます。
- 建築確認申請書(の副本)
- 設計仕様書、パンフレットなど、省令準耐火構造であることが明記されているもの
- ハウスメーカーや工務店が発行した「省令準耐火構造建物証明書」
- 住宅金融支援機構の「適合証明書」
これらの書類は、いわば、あなたの家の保険料を半額にするための「割引クーポン」のようなものです。
少し手間がかかるかもしれませんが、その価値は計り知れません。ぜひ、探してみてください。
もしかして我が家も?省令準耐火構造・かんたんチェックフロー
YES/NOで、あなたの家の可能性を探ってみましょう!
- Q1. あなたの家が建てられたのは、2000年以降ですか?
→ YESなら、可能性アップ!省令準耐火の考え方が普及してきた時期です。 - Q2. 住宅ローン「フラット35」を利用しましたか?
→ YESなら、可能性は非常に高いです!適合証明書を確認しましょう。 - Q3. 大手のハウスメーカーで建てましたか?
→ YESなら、可能性あり。近年の住宅は、標準仕様で採用していることが多いです。 - Q4. 建築時のパンフレットや仕様書に「耐火」「防火」「ファイヤーストップ」といった言葉がありませんか?
→ YESなら、大いに可能性があります!書類を詳しく見てみましょう。
※一つでもYESがあれば、諦めずに確認する価値は十分にあります!
省令準耐火じゃなくても諦めない!保険料を賢く節約する実践テクニック
「うちの家は、残念ながら省令準耐火構造ではなかった…」
そうがっかりされた方も、どうか気を落とさないでください。
保険料を劇的に半減させる「裏ワザ」は使えなくても、あなたの火災保険料を、今よりもずっと賢く、そして着実に安くするための「正攻法」は、まだまだ、たくさん残されています。
この章では、たとえあなたの家が、一般的な木造住宅(H構造)であったとしても、今日からすぐに実践できる、火災保険料を最大限に節約するための、7つの具体的なコツを、一つひとつ丁寧にご紹介していきます。
これらのテクニックを組み合わせることで、あなたの保険料は、きっと、もっと納得のいく、スリムなものへと生まれ変わるはずです。
コツ1:補償内容を「断捨離」する
保険料を節約するための、最も基本的で、そして効果的な方法が、補償内容を、あなたの家の実態に合わせて、オーダーメイドで設計し直すことです。
今の火災保険は、昔のようなパッケージ型ではなく、必要な補償と不要な補償を、自分で自由に選べるようになっています。この「選択の自由」を、最大限に活用しましょう。
その中でも、特に大きな節約効果が期待できるのが、「水災補償」の見直しです。
お住まいの市区町村が公表している「ハザードマップ」をインターネットで確認し、あなたの家が、洪水や土砂災害のリスクが極めて低い、安全な立地にあると判断できる場合、この水災補償をプランから外すことを、積極的に検討してみてください。
火災保険料全体の中で、水災補償が占める割合は決して小さくありません。これを外すだけで、保険料が年間で数千円から一万円以上、安くなることも珍しくないのです。
コツ2:免責金額(自己負担額)を最適化する
次に、保険料をコントロールするための、強力なレバーとなるのが、「免責金額(めんせききんがく)」の設定です。
免責金額とは、万が一、損害が発生した際に、ご自身で負担する「自己負担額」のことです。
この自己負担額を、高く設定すればするほど、年間の保険料は安くなる、という関係にあります。
例えば、「窓ガラス1枚程度の、数万円の小さな損害なら、保険を使わずに、貯金から支払っても大丈夫」と考えるのであれば、免責金額を、一般的な5万円から、10万円や20万円に引き上げることを検討してみましょう。
そうすることで、毎年の保険料の負担を、目に見えて軽くすることができます。
「小さな損害は、貯蓄で備える。自分ではとても対応できない、数十万円、数百万円といった大きな損害にだけ、保険の力を借りる」
このような、保険と貯蓄の役割分担を明確にすることが、保険と賢く付き合うための、大切な考え方です。
コツ3:家財保険の金額を見直す
火災保険は、多くの場合、「建物」の補償と、「家財」の補償の二階建てになっています。
この「家財」の保険金額が、知らず知らずのうちに、過剰な設定になっていないか、一度見直してみることも、節約への近道です。
「もし、今、この家にある家具や家電、洋服が、すべてなくなってしまったら、買い直すのに、一体いくらかかるだろう?」
この機会に、一度、冷静に計算してみてください。
保険会社のウェブサイトなどでは、家族構成や年齢から、おおよその家財評価額を自動で算出してくれるツールもありますが、それはあくまで一般的な目安です。
「うちは、そんなに高価なものは持っていないな」と感じるのであれば、その目安の金額よりも、少し低めに設定することで、その分、保険料を安くすることができます。
コツ4:保険期間を「長期」にする
火災保険の契約期間は、1年から、最長で10年まで、自由に選ぶことができます。(2022年10月以降、最長5年になりました)
そして、多くの保険会社では、1年ごとに契約を更新していくよりも、5年や10年といった、まとまった期間で契約した方が、「長期契約割引」が適用され、1年あたりの保険料が、割安になるように設定されています。
もちろん、長期契約の場合は、契約時に保険料を一括で支払う必要がありますが、その分、トータルで支払う金額は、毎年更新を続けるよりも、安く抑えることができます。
今後も、その家に長く住み続けることが決まっているのであれば、可能な限り、長期での契約を検討するのが、賢い選択といえるでしょう。
コツ5:割引制度をフル活用する
自動車保険に、ゴールド免許割引や、自動ブレーキ割引などがあるように、火災保険にも、さまざまな割引制度が用意されています。
これらを、一つでも多く見つけ出し、適用させることが、保険料を節約するための、地道で、しかし確実な方法です。
例えば、以下のような割引制度があります。
・オール電化割引:ご自宅がオール電化住宅の場合に適用されます。
・WEB申込割引:インターネット経由で、直接保険会社に申し込む場合に適用されます。
・ノンスモーカー割引:同居の家族に喫煙者がいない場合に適用される、ユニークな割引です。
これらの割引制度の種類や、割引率は、保険会社によって大きく異なります。
見積もりを取る際には、ご自身の家の設備などを正確に伝え、「何か、適用できる割引はありませんか?」と、積極的に質問してみる姿勢が大切です。
コツ6:地震保険の割引もチェックする
火災保険とセットで加入することが多い「地震保険」。
実は、この地震保険にも、建物の性能に応じた、いくつかの割引制度が存在します。
これらを適用できれば、火災保険と地震保険を合わせた、トータルの保険料を、大きく引き下げることが可能です。
代表的なものに、以下の割引があります。
・免震建築物割引(50%割引)
・耐震等級割引(耐震等級に応じて10%~50%割引)
・耐震診断割引(10%割引)
・建築年割引(10%割引)
ご自身の家が、これらの基準を満たしているかどうかは、建築確認申請書や、住宅性能評価書などで確認することができます。
特に、比較的新しい住宅にお住まいの場合は、これらの割引が適用できる可能性が高いので、ぜひ一度、確認してみてください。
コツ7:必ず「相見積もり」を取る
そして、最後に、最も重要で、そして最も確実な節約術をお伝えします。
それは、火災保険を、決して一社だけで決めない、ということです。
これまでお話ししてきたように、保険料や割引制度は、保険会社によって、本当に千差万別です。
全く同じ条件で、同じ補償内容の見積もりを取ったとしても、A社とB社とで、年間の保険料が1万円以上も違う、ということは、ごく当たり前に起こります。
そこでお勧めしたいのが、インターネット上にある「火災保険一括見積もりサイト」の活用です。
一度、あなたの家の情報を入力するだけで、複数の保険会社から、同時に、無料で(一部有料)見積もりを取り寄せることができ、手間をかけずに、最も条件の良い保険会社を見つけ出すことができます。
最低でも3社以上を比較検討すること。それが、あなたが損をしないための、絶対的なルールです。
火災保険料節約アクションプラン
この7つのステップを実行して、あなたの保険料を見直しましょう!
- ☐ 補償の断捨離:ハザードマップで水災リスクを確認しましたか?
- ☐ 免責金額の最適化:自己負担額を少し上げて、保険料を安くする検討をしましたか?
- ☐ 家財金額の見直し:本当に必要な金額になっていますか?
- ☐ 長期契約の検討:5年や10年の契約で、長期割引のメリットを受けますか?
- ☐ 割引制度の活用:オール電化など、使える割引をすべてチェックしましたか?
- ☐ 地震保険割引の確認:耐震性能を示す書類はありますか?
- ☐ 相見積もりの実施:一括見積もりサイトなどで、3社以上を比較しましたか?
「高い」には理由がある。「賢い選択」で、最高の木造ライフを
木造住宅の火災保険料が、なぜ鉄骨造やマンションに比べて高めに設定されているのか。
その長い旅の終わりに、私たちは、それが統計データに基づいた、合理的な理由によるものである、という事実にたどり着きました。
しかし、同時に、その大きな「木造」という括りの中には、あなたの家の性能や立地といった、個別の状況が、まだ正しく評価されていない「伸びしろ」が、たくさん隠されていることも、お分かりいただけたのではないでしょうか。
その最大の可能性が、「省令準耐火構造」の確認です。
もし、あなたの家がその基準を満たしていれば、保険料は劇的に安くなります。
たとえそうでなかったとしても、補償内容をあなたの暮らしに合わせてカスタマイズしたり、割引制度を一つひとつ丁寧に探し出したりといった、「賢い選択」を積み重ねていくことで、保険料というコストを、あなたの家の実力に見合った、適正なレベルへと、確実に最適化していくことができるのです。
保険料への漠然とした不安や、不公平感を解消すること。
それは、木のぬくもりに包まれた、心から安心して暮らせる、最高の木造ライフを手に入れるための、とても大切で、そして、あなた自身にしかできない、重要な一歩です。
この記事が、あなたの家計と、かけがえのない暮らしを守るための、最適な火災保険選びの、確かな羅針盤となれたなら、これほどうれしいことはありません。
コラム一覧